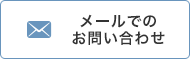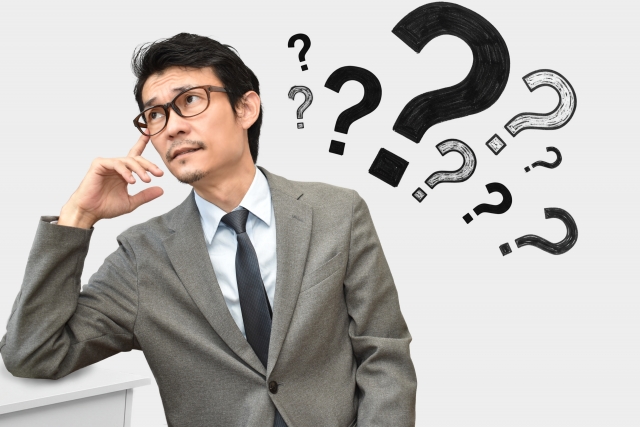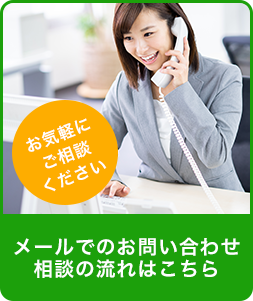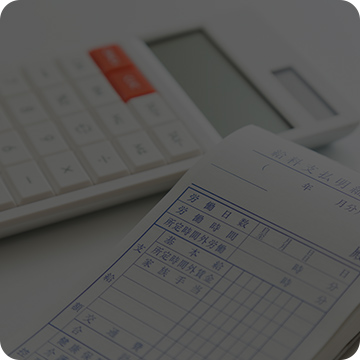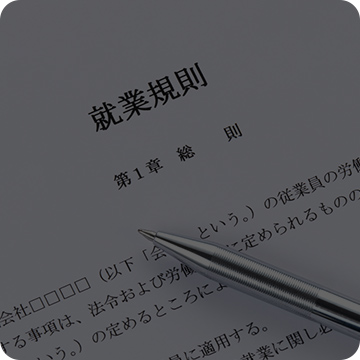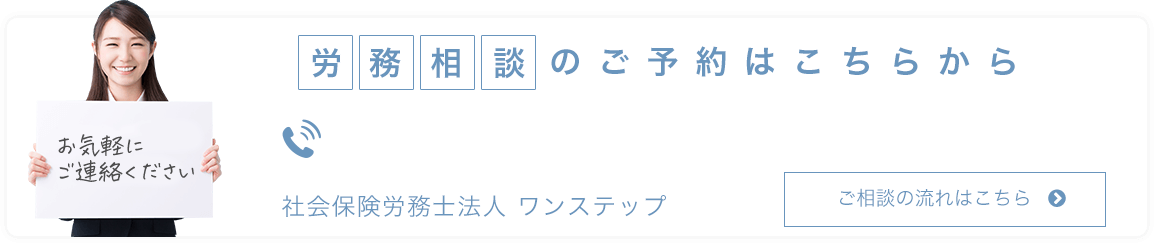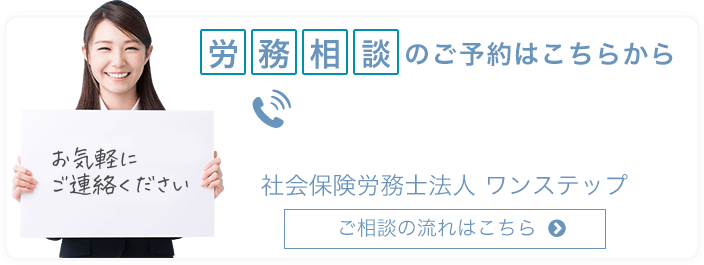当法人の労務相談顧問は、「迅速なレスポンス」、「杓子定規ではない寄り添った回答」が特徴で、法改正内容や対応事項のような基本的なところから労使間のトラブルの対応方法、問題社員への対応方法等多くの相談に対応しております。
受給した助成金に税金はかかる?正しい会計処理の方法
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
当法人では、労務管理や助成金申請を通じて数多くの企業のサポートを行っております。
その中でも、「助成金を受け取ったけれど税金の扱いが分からない」「会計処理はどうすればいいのか」というご相談を多く頂戴します。
本記事では、助成金・補助金に関する税務上の取り扱いと、
正しい会計処理の進め方について、実務担当者の視点から分かりやすく解説します。
1. 助成金・補助金に税金はかかるの?
結論:原則として課税対象です。
-
法人なら「法人税」、個人事業主なら「所得税」の対象になります。
-
一部に非課税となる給付(例:一時所得扱い)もありますが、ごく一部です。
-
消費税は「モノやサービスの取引」ではないため 非課税 です。
👉 「もらって終わり」ではなく、税務処理まで見据えた管理が大切です。
2. 会計処理の基本ポイント
助成金を受け取った際の会計処理の基本は以下の通りです。
-
勘定科目の設定
通常は「雑収入」または「特別利益」で処理します。※支給決定済みで未入金の場合は「未収入金」を使用します。
-
収益計上の時期
「申請日」ではなく、「支給決定通知日」が属する会計年度で計上します。 -
消費税の扱い
助成金自体は非課税ですが、設備導入などに活用した場合、
仕入税額控除との整合性に注意が必要です。
3. 税務上の注意点と圧縮記帳の活用
助成金を受け取った後は、税務面にも気を配る必要があります。
-
課税・非課税の判断
→ 事業目的で支給される助成金は課税対象。
個人向け給付金は非課税になる場合があります。 -
税負担が増えるケース
→ 設備を購入して助成金を活用した場合、収益増加と資産計上が重なり、
一時的に法人税が増えるケースもあります。 -
圧縮記帳の活用
→ 助成金で取得した資産の帳簿価額から助成金相当額を控除し、
一時的な税負担を抑える方法です。
例)設備1,000万円購入、助成金500万円 → 帳簿価額500万円で処理。
→ 税務申告での添付や届出が必要なため、専門家に確認が必要です。4. 実務的なチェックリスト
実務上、「助成金を受給したけどどう会計処理すればいいか分からない」「税務上どうなるか不安」という声が多いため、以下のチェックリストを提示します。
-
□ どの助成金/補助金か?(制度名・目的・支給根拠)
-
□ 自社が法人か個人か?その受給主体は?
-
□ 受給金額・入金予定日・決定通知日を確認
-
□ 支給決定日がどの会計年度に属するか?
-
□ 勘定科目の設定は「雑収入」または「特別利益」になっているか?
-
□ 入金前に未収入金を使った仕訳が必要か?
-
□ 固定資産を取得した場合、圧縮記帳を検討しているか
-
□ 消費税の仕入税額控除に影響がないか?(特に設備購入+助成金活用時)
-
□ 税務申告で「別表」の添付や開示が必要か?
-
□ 帳簿・仕訳を税理士・社労士と共有しているか?
これらを踏まえて、助成金を戦略的に活用しつつ、帳簿・税務リスクを抑えるための体制を整えることが重要です。
5. 社会保険労務士法人ワンステップに相談するメリット
助成金は「申請して受け取る」だけでなく、
受給後の会計・税務・労務をトータルで整備することが不可欠です。-
和歌山トップクラスの助成金支援実績
-
労務管理・就業規則・給与制度まで一体的に支援
-
申請から交付後の税務・会計処理相談までワンストップ対応
👉 詳しくはこちら:社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
6. まとめ
ご相談はワンステップへ
申請はもちろん、その後の労務・会計・税務を一体的に整えたい方は、
👉 社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト へお気軽にご相談ください。 -
- あわせて、最新の助成金情報は
👉 厚生労働省HPでもご確認いただけます。